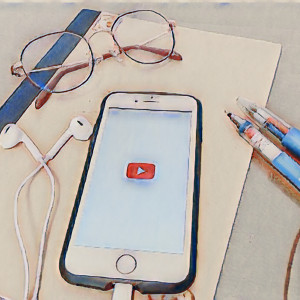ダレカの物語(大学生 クロさん)
―時は西暦2050年。人とロボットが共生する街、デイトナ。
地球外環境の研究者ジャン・ハッカーソン博士は、月面で採取した砂岩を電子顕微鏡で観察していた。
丁度正午あたりだった。秘書がお昼休憩をとりに席を立った、そのとき。
シュンッ!
確かに何かが高速で動いた。ナノサイズの超微生物が確かにいたのだ。
「や、やったぞ。とうとう見つけたんだ」
博士は集中するために付けていた耳栓をつけたまま、興奮して外へと飛びだした―
―上書き保存しました―
ふうう、と一息吐いて腰を伸ばし、私は耳を塞いでいたイヤホンを外した。
時は西暦2021年夏。現実世界の日本、とある田舎町のワンルーム。
冷蔵庫から冷えた缶ジュースを取り出して、おでこにあてた。もちろん冷たい、そしてジメジメとした暑さとフル稼働させて熱を持った頭をほんの少し涼ませてくれる。だから私はペットボトルより缶の方が好きだ。
しばらく頭を冷やして、またパソコンの文字ばかりの画面へと目を向ける。
さて、ここからこの「ダレカの物語」をどう展開させていくか。
ふと時計を確認するとPM十時、まだ夕食さえ食べていなかった。急いでカップ麺にお湯を注いだ。
去年春の「あれ」以降、私の生活はずっとこんな感じの時間という概念が希薄なものになった。
「あれ」つまり、パンデミックは友人の少ない理系大学生である私にとってそれほど苦なものではなかった。週に一、二回は登校して、あとは家で何となくパソコンから流れるBGMと化した講義を聞いていればいい。興味のある講義だけ聞いていればいいのだ。
最初の頃はなんとなく夜中までゲームをするか映画を観ていた。朝は講義開始と共に起き、なんとなく朝食のパンをかじり、そして講義が終わればなんとなく昼食代わりのエナジードリンクを飲む。
だが、そういう生活が三か月も過ぎると「果たして自分は大丈夫なんだろうか?」と何とも言い切れない謎の不安感と虚無感に苛まれた。毎日が淡々と過ぎていき、私一人がこのコロナ世界に取り残されているかのような、そんな錯覚を感じたのだ。
こういう時、SNSという情報源は凶器となる。同じ大学の人や知り合いや、高校の旧友たちは、コロナ禍であってもそれなりに楽しそうな文章や写真をあげていた。
「やばい、このまま私だけ……私だけ……」
そんな去年の夏ころ、一冊の本と出合った。小松左京著「復活の日」は、まさに今のコロナパンデミックを予見していたかのような、まさに予言書だった。私は、小松左京の書いたSF(サイエンス・フィクション)の世界観に圧倒された。SFといえば星新一のショートショートを思い浮かべる私にとって、この本の文章の濃厚さと厚みのある未来への創造はまさに理系大学生の心を面白いようにくすぐった。
私もこんな物語を書きたい。単純な興味から、私の紡ぐ「ダレカの物語」が始まった。