
海苔バナ のり子さん(仮名)のはじまり
母が亡くなってからの日々は、自分の引っ越しやいろんな手続きで怒涛のようにすぎていった。
頭を休ませ、体を動かすために10分とか15分とか散歩に出るのが現実逃避でもあり。
“あ、今日は風があるな”、“夏っぽくなってきたな”ってボンヤリ天気を感じたり、“あー私はこんなグルグルぐちゃぐちゃしているのに、町とか世間とかのんびりしているな、普通に日常があるんだな”ってホッとしたりする時間。
ふと、母家の隣にある倉庫を見上げる。
父が海苔屋を辞めてからは物置になって放置されていた。
両親は起きている時間はほとんど倉庫にいて、ストーブでお湯を沸かし、仕事の合間1分くらいでおにぎりを詰め込んで、コーヒーを飲む時もその場で立って飲んでいた。
倉庫は私たち家族の青春。
なのにもう生きたエネルギーが流れていない。
明かりが灯ることもない活気のない倉庫は、以前より暗く、静か。
そこに私の宝物である本を入れる黒いスチールラックを買って設置してみる。時が止まった倉庫に、真新しいラックにずらっと並ぶ海苔やその他の私の大切な本たちが1600冊ほど。私はラックを眺めているうち、この海苔の作業場に再び灯りを灯したくなった。妄想が膨らむ。
私は不謹慎かなと思いながらも喪中の間にリノベーションを始めることにした。
このポッカリ母だけがいなくなった家で、このワクワクしない町で自分が楽しくいるために“はりあい”を作りたかった。
東京でやろうと思っていた“海苔バナ”の活動、同じことを千葉の田舎でやろうとしても叶わない。でも東京では到底持てなかった“場”をUターンしたことで手に入れたので、静かな住宅街で生活しながら無理なくできることを探りながら、やりたいこと1つ1つを前向きに試していこう。
海苔倉庫のリノベーションを進めていくと、出てくる荷物や書類に、海苔店の歴史も詰まっていて。父の記憶もよみがえり、初めて聞くような話もあって面白い。
壁は母の好きだった黒。海苔の黒。
入り口には暖簾。海苔みたいな生地を選んで手作りしようと、母が集めた裁縫道具や大量の材料を取り出してみる。色とりどりの紐やボタン、レースやその他いろいろ。子供の頃、母の服を私好みにアレンジしてくれたことを思い出す。
完成した暖簾は風に揺られ、光を浴びて海苔のように艶やかだったり、海の底みたいに深い色だったり様々な表情を見せる。
この暖簾のように色んな表情をもつ場になっていく。
“地域のために”とか“町のため”とかではなく。私の器ではそんな大それたことは無理なので。
あくまでも“自分が楽しむため”の場。
“コミュニティスペース”でも“サードプレイス”でもなく。居場所は誰かに用意してもらうものではないと思っている。ただ、“一緒に楽しむ”中で、学校やこの街がつまらないとか、大事な人を失ったとか、どうやって働こうかとか、家族や先生とは違う体験を分けてあげられると思う。生きている間にしか分けてあげられないから。
“いかに生きるか、いかに閉じるか”
私は母を亡くして、死生観が大きく変わった。
それまではさほど“死”を意識せず“いかに生きるか”と思っていたが、母がいないこの世に正直、全く未練がなくなって。ある日突然命が終わるということを経験したら“いかに閉じるか”に焦点が変わった。
私にとって“生きる意味”は“閉じる準備”。
でもそれは暗い重いものではなく。気持ちの土台としてはとても強いもの。
ボウボウッ
今日も強い風が吹く。
頬に、背中に、強い風を感じる。
母が亡くなってから、切れなくなった私の長い髪を揺らす。
私の住んでいるところは高台のせいもあって、わりといつも強風。
風を感じると母を思う。
怒りなのかなんなのかメッセージの内容は分からないけど、母が何か言っているって感じる。姿はなくても、もう名前が二度と呼ばれなくても、強い風は変わらずそばにある。
『お前にできるわけない』
海苔についてやりたいと叫び続けていた私に母が言った言葉。
でも母のスマホには、私がやっている海苔のインスタに使える写真が何枚も撮ってあった。
口ではああ言いながら、応援してくれようとしていた気持ちも受け取った。
私がどんなことをしたかったのか、いずれ地元に帰ってやろうと思っていたことをやっていこう。
現世でできる全てをやりきって、あの世で母に会えるとするなら胸を張って会いたいから。
海苔についてもっと知りたい。
創造性のある人、行動力のある人に出会いたい。
海苔は一期一会。
自然界と人の手で作り上げる奇跡。当然だけど、同じ海苔は手に入らない。
それと同じように日々も同じではない。
当たり前なんか一つもない。
風の当たらない母の仏壇前の風鈴が、小さくチリンと鳴る。
あぁ、お花の水変えたっけ?
母が何か言っている。
私は一息ついて 今日も 風を 感じる
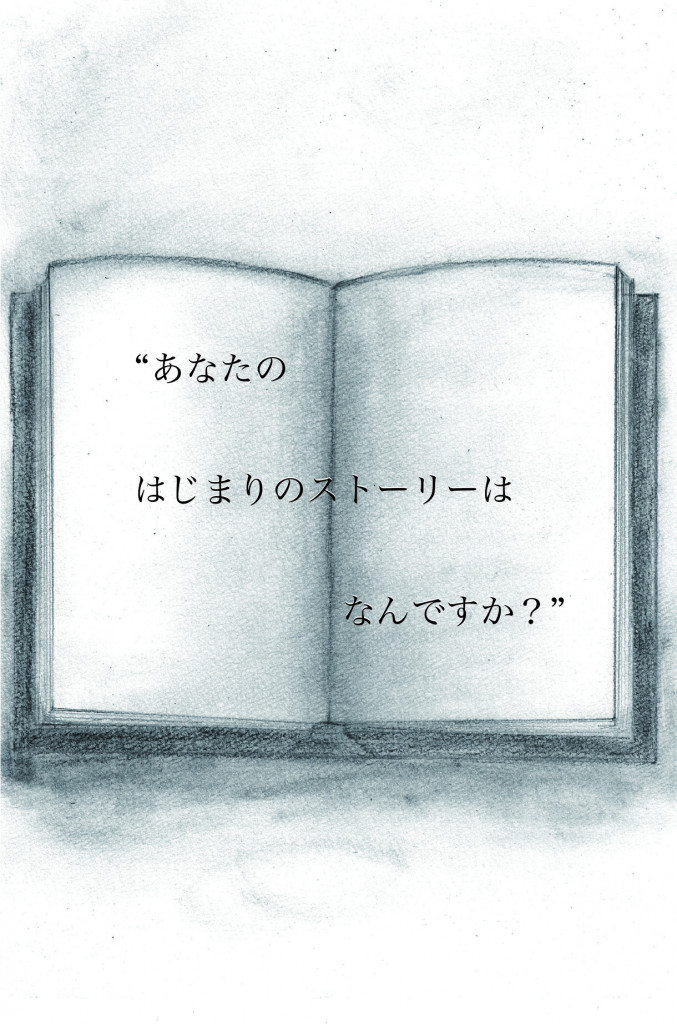
※この小説は、出演者本人のインタビューを元に、Sainomedia編集部で創作した小説となります。



