
やわらかん’s cafe オーナー 鈴木公子のはじまり
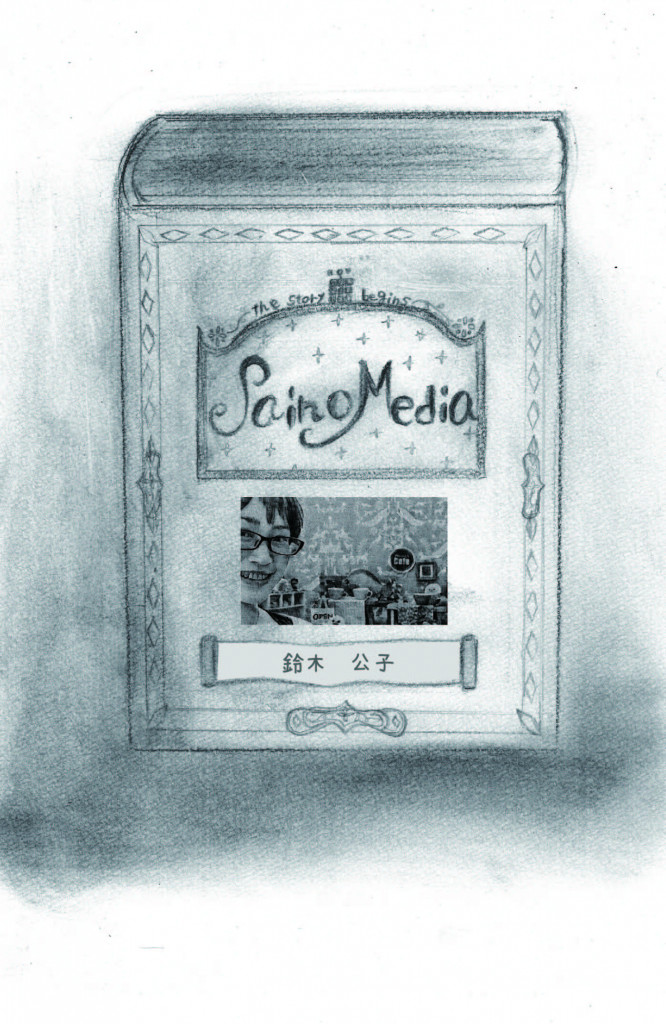
わたしがマーマルと出会ったのは、いつだったかな。
きっとあのとき、あの出会いからすべてははじまったんだと思うの。
葛西臨海水族園で、ちょっぴり地味な色合いのわたしを抱き上げて、マーマルはやさしくほほえんでくれたっけ。
あ、ちなみにマーマルは哺乳類って意味でママとはちょっと違うの。
わたしは、その当時、しじみの幼稚園で働いてて、ぬいぐるみのための旅行会社をやりたくて脱サラしようと思っていたところだったの。
それから、ナウいコーヒー屋に行ったことで、カフェもやりたいって思ってたことを思い出してみんなに相談したら、みんなわたしの夢を応援してくれて、ほんとに嬉しかったの。わたし、うれしくって涙が溢れてきちゃった。
最初のお客さんがカフェに来てくれた時の感動は、今でも忘れられないわ。
マーマルが“やわらかん’sカフェ”のオーナーになってくれて、私を店長にしてくれて、わたしはほんとに幸せな女の子よ。
いつもはなかなか聞くことがない、わたしの大切なマーマルにインタビューしちゃおうかしら。

カレイちゃんからマイクが回ってきたので、今日は私の昔話をちょっとだけ。
今思えば私のぬいぐるみ愛の本当の始まりはこの時からだったのかもしれない。
それは私が3歳くらいの頃。
うさぎをモチーフにして赤ずきん風にした、垂れ耳のうさぎさんのマイメロディーというキャラクターのぬいぐるみ。
大好きで、大好きで、どこに行くのにも一緒。
母が作ってくれたニットのボーダーワンピースがとってもかわいくて。
かわいがりすぎてボロボロになって、ボディが擦り切れて、そこからオレンジの四角いスポンジが、コロリ、コロリってよく飛び出しては、ボディにしまっていた。
そこから常に私のそばには大好きなパートナーが1体必ずいるようになった。
次の出会いは、小学生の頃。
近所にはファンシーショップがあって、そこにはいろんなぬいぐるみさんたちがいて、買えないけど、よく行っては友達とそのぬいぐるみ達と遊んでいた。
そんなある日、売り場にあった私の一番お気に入りのぬいぐるみをお迎えすることになった。
しろくて、雪だるまみたいな姿、ちょこんと頭についた赤いトサカ、オレンジ色の可愛いお口。
黒目がちなおめめの周りにフェルトがついた、にわとりのぬいぐるみ。
私は、このにわとりのぬいぐるみに“コッコちゃん”と名付けた。
この時から、どんな時も学校以外はコッコちゃんとずっと一緒。
実家は、ウナギのかば焼きを売るお惣菜屋さんで、遊びの延長で、幼稚園の時はじゃがいもを剥いたり、小学生になると接客をするなど、いつの間にか手伝いをしていた。
お店の手伝いが終わると、お店の前で遊んだり、大好きなぬいぐるみと遊んだりしていた。
妹はカバのぬいぐるみのしろちゃんがお気に入りで、私たち姉妹はどんな時も大好きなぬいぐるみと常に一緒。
妹が「ただいま〜」と家に帰ってくると、私が「おかえり〜」と妹の部屋からコッコちゃんをひょっこり出して動かしながらお出迎えする。
普通の会話も、大好きなぬいぐるみを通して、身振り手振りで声色を変えておはなしするのが日常茶飯事。
コッコちゃんは、どんな時も私の話を聞いてくれて、優しく微笑みながら、いつも私のそばにいてくれて、私にとってかけがえのない存在になっていった。
小中高と成長しても、ぬいぐるみに対する愛はずっと変わることはなかった。
高校生のある日。
とうとう運命の日はやってきた。
以前から親が、私のぬいぐるみ好きなのを心配しているのも、よく思っていないこともひしひし感じていた。
だからいつか言われると、そんな日が来るんじゃないかって、、思ってはいた。
でも、、でも、、
今でもキュゥって胸を締め付けられる。
「このままじゃ大人になれないから、ぬいぐるみは捨てなさい。」
とうとうこの日が来てしまった。
私はこの家のルールは守らなきゃという思いが強く、身が切られる思いでさよならをすることにした。
でももう触れることができなくなるなんてぜったいいやだ。
一部でもせめて、せめてお守りに持っておきたい、、、
「コッコちゃん、ごめんね」
震える手でコッコちゃんの尻尾に、ハサミを入れた。
シャキンッ
冷たい、鋭い音が、胸に、刺すように響いた。
私は、小さな愛しい尻尾を抱きしめて、大切に引き出しにしまった。
こうして私は、表面上はぬいぐるみとお別れした。



