
海苔バナ のり子さん(仮名)のはじまり
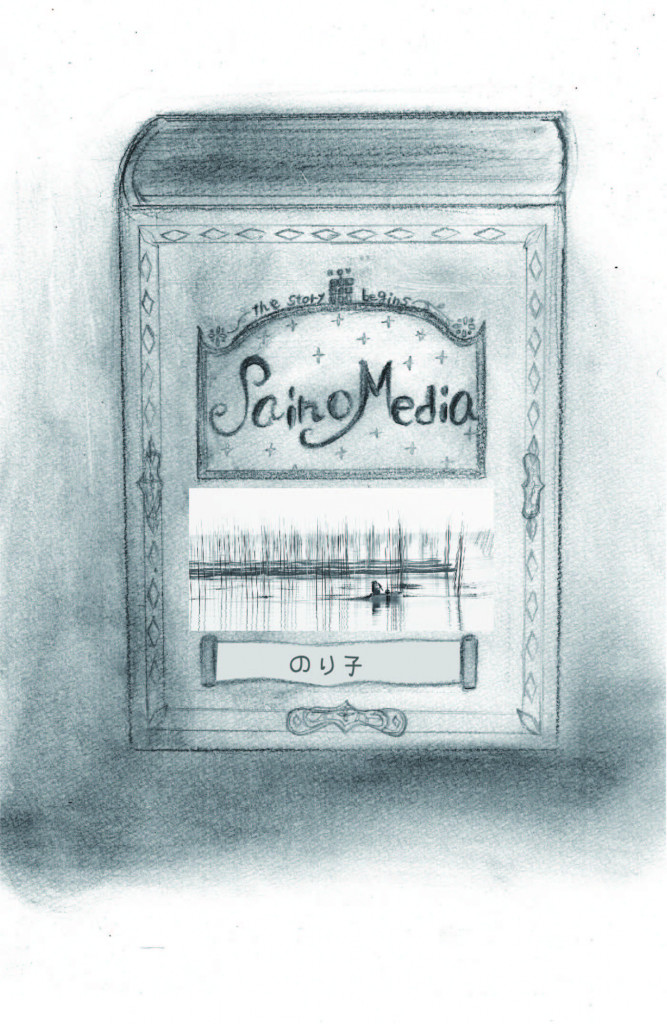
さよなら東京、向島。とうとうお引越し。15年住んだ部屋。
がらんどうになった部屋は音がやたら響いてなんか寂しい感じ。
向島はスカイツリーができて地価が上がったけど、15年間家賃は据え置きだった。何より“向島”っていう住所、気に入ってた。部屋も大好きだった。開放感のある天井に、スカイツリーの花火がみえたり。次はどんな人が暮らすんだろう。
支払った家賃は単純計算で1500万円超!
「その価値があったか」と父。「プライスレスな経験ができた」と私は答える。
この地域には人なつっこい人が多かった。
向島の人はぶっきらぼうに感じても“向島が好き”って伝えればみんな優しくしてくれる。
心を開いて飛び込むと、(いい意味で)お節介な人が多い。この“お節介”には本当に助けられてきた。新しい仲間を面白がるそんな下町に私もだんだん染まっていっていた。
私はこの大好きな街での生活を置いて、実家の家業を継ぐため帰る。
親の心配もあったし、いつかこの日が来ることも分かっていた。
でも念願の家業を継ぐお許しが出たのに、帰る地元にはワクワクがない。
私の地元は千葉県の内房(うちぼう)エリア、袖ケ浦市というチーバくんで言うと、お腹あたり。東京駅まで快速電車で1時間ほど、首都圏への通勤はできなくないけど“小旅行”感が否めない距離。
工業地帯に埋め立てられる前、このエリアでは海苔の養殖が盛んだった。今、みんなに多く食べられている海苔の品種はナラワスサビノリ。ナラワ=奈良輪。袖ケ浦市に現存する地名。そんな地域で私は海苔問屋の娘として育った。海苔を仕入れ、加工してお店に下ろすという仕事。
海苔はとても繊細な食べ物で、毎日の天気や湿度の変化などによって乾燥時間を調節したりと気を使う作業も多く、父はいつも真摯に向き合い、寝る間も惜しんで働いていた。
私は子供の頃、両親が横になって寝ている姿を見たことがない。朝は近くの養鶏場の鶏が泣き出す頃に飛び起きて、夜中1時〜2時ごろまで働いていた。
そんな両親を見ていたせいか早く働きたいという思いは幼い頃から強かったと思う。
学校から帰ると“今日あったこと”を聞いてもらいたくて、家の敷地にある海苔の作業場、通称“倉庫”へ行く。
「あのね、今日ね…」
「手を動かせ」
仕事に夢中な2人は手を止めて私の話を聞くなんてことはない。生返事ばかり。何かしてないとそこにいるのを許されないような雰囲気。
私は袋に貼るシールの枚数を数えたり、決められた位置にシールを貼ったりと簡単な作業を振られ、お小遣い制ではなかったので海苔の作業を手伝ってお手伝い賃みたいなものを稼ぐスタイルだった。
簡単な作業でも「助かった」と言われるのが嬉しくて、役に立つこと、仕事をして対価を得る基本は家で学んだ。
こき使われてるって思ってイヤだった時もある。
でも子供の頃「触るな」と言われていた作業がひとつずつ任せてもらえるようになってくると役に立ってるって実感があって嬉しく思うこともあった。
両親は厳しく、特に母は激しい性格だったので怒鳴られるのは日常茶飯事。
「だらしがない」「門限を破った」とか、小さな理由で大怒られして、大泣きして柱にしがみついても力づくで家から追い出されたり。
テレビも見ちゃだめで、テレビは置いてもなかったので話題についていけず、つらい時期もあった。マンガも買ってもらえず、友達から借りたりしたけど、本と雑誌はわりとなんでも買ってもらえたので、今となっては雑誌の世界に憧れたのも文化の入り口が雑誌だったのかもしれない。
「お前に嫌われることは痛くも痒くもない。お前が世の中に出て困らないように、お前のためなんだよ」母は私によくこう言っていた。
テストで96点も「100点ではない」、学年順位が一桁でも「上がいる」、褒められることはまずない。習い事も門限にも厳しく、学校も町も私には合ってない気がして、窮屈で退屈なこの町を1日でも早く出て、親の目の届かない東京で自由に暮らしてみたいと思っていた。
そんな子供時代に、マイガールという映画を観た時、その中で女の子が着ている刺繍入りのチュニックみたいな服が可愛くて。それがヒッピー風の洋服だと知って、ピッピー文化に興味を持つきっかけになった。
その頃ジッパーというファッション雑誌にはヒッピー風の服がいっぱい載っていて、憧れたけど高価で買えないので、母の独身時代の服のボタンを変えたり、刺繍をしてもらったりしてヒッピー風にリメイクしてもらったりしていた。
ヒッピーファッションに始まり、音楽、そして次第に考え方に惹かれていった。
私は窮屈な思いを抱えながらも中学生になり、いろいろしんどいこともあったけど、英語教室や手話教室など、学校以外の大人と過ごす時間に救われた。
そんな中学生活終盤の3年の秋、高校進学において大事な時期に彼氏ができた。
別な高校に行ったら別れるかもって思い込んで、彼が行ける高校に合わせることにした。
もともと目指していた高校から偏差値は半分。地元では悪名高き高校。
通っていた塾から「その高校への進学は塾の名に傷がつくから、進路を変えるなら塾をやめてくれないか。名前さえ書いて、各教科1問ずつ正解すれば合格する高校だから、塾の必要はないよ」と言われたり、担任には「急いでは事を仕損じる」と明言をもらい、学年主任が家を訪ねてきたり、大波乱の反抗期を経て、親との関係も最悪なまま晴れて彼と同じ高校に入学した。
「一時的な気持ちに惑わされて人生棒に振らない方がいい。気持ちは絶対変わるから。」
母からそんなことを言われていたけど、その時の私はそんなわけないと思っていた。でも進学して環境の変化とともに気持ちが薄れ、この恋は終わりを迎えた。



