
ファミリーヒストリー記録社 代表 吉田富美子のはじまり
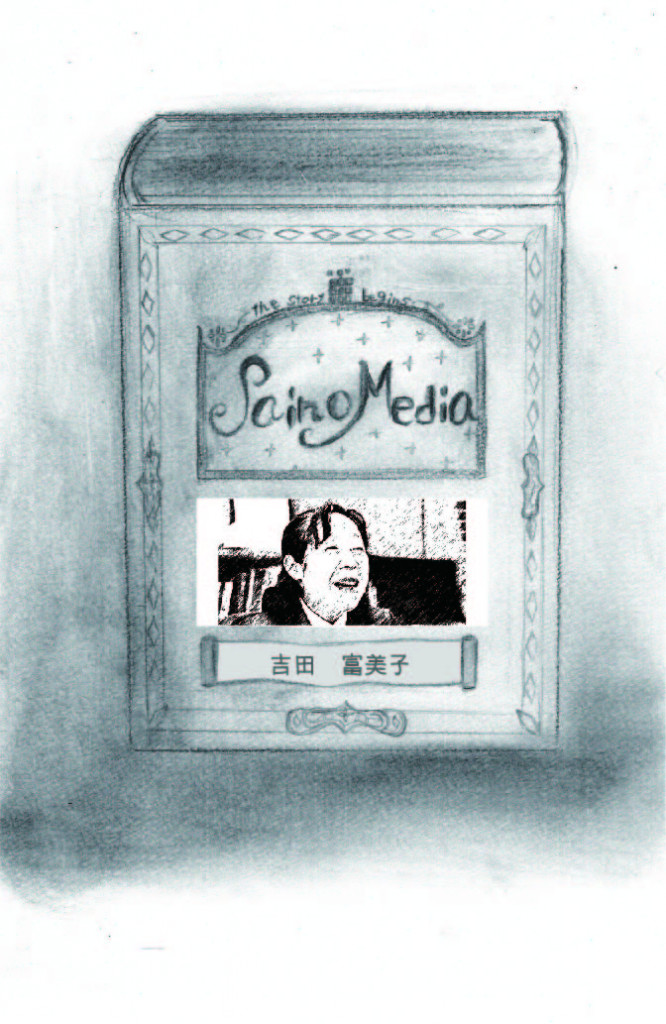
オレは終戦の知らせを故郷から遠い長野の地で聞いた。
「根室で空襲があったからもう誰もいないよ」
「みんな死んじゃったよ」
そんな言葉が耳に届く。
でもオレは故郷に近い北海道の根室を目指した。
やっとの思いでたどり着いた根室は、見渡す限り真っ黒焦げの焼け野原になっていた。
何もなくなった市内の景色。
愕然とする。
でも、何もなくなっても幸い家族が、親戚が生きていた。
オレは生きていくために、根室市内の歯舞に家を探し、小学校の用務員になったり、大工をやったり、昆布の行商をしたりして、その先で出会った女性と結婚した。
これは北の大きな大地に芽生えた小さな物語。
そしてこれが私たち家族のはじまり。
そして“私”のはじまり。
家族の物語は、自分が一人ではないことを教えてくれるご先祖が残してくれた大切な物語。
自身の存在する意味、価値、重さを知ることができる。
いくつもの偶然でつながってきた命、今存在していること、今生きていることはそれだけで特別なことだと気づく。

「あぁ〜もうほんと寒い!!」
私は、家に入ると雪を払いながら、いつもの肌を突き刺すような外の寒さに耐えられず思わず呟いた。
とにかく寒いからこんなところで暮らしたくないと心の中で毒気づく。
私の住む北海道の根室市歯舞(はぼまい)は、冬は本当に寒い。そして夏も半袖を着たことがないくらい涼しい。
歯舞といっても北方領土の方ではなく、根室市内からは少し離れた根室半島の中の地域で、周りは隣近所には家がなく、見晴らしがいい牧草地帯が広がっていて、海まで歩いて2分。吹き曝しのためか、風が強くて冬はとにかくものすごく凍れる。実家は納沙布岬に行く一本道に、日用品や食料品などなんでも売っている商店を営んでいた。
「ちょっと仕入れに行くから、店番お願いね」
家の奥から父の声が聞こえる。
母が小5の時に他界してから、父と姉2人と私、弟が1人の5人暮らし。
父が市場や仕入れに出かける時は、店番を代わる代わるするのが日常だった。
私は、小学校の頃からSFや推理小説とか本を読むのが好きで、学校にある本は誰よりも先に読み終えていた。漫画も少年誌、少女誌の両方読んでいるほど大好きで、漫画家に憧れて、出版社に投稿したり、中学では漫画同好会を作ったりした。でも小学生でプロデビューする人もいて、中学校の頃には漫画家の夢は諦めていた。
中学校ではみんな制服のスカートのところ、スカートが嫌で私だけスラックスで登校したり、私が変わったことを言ったりするので、ユニークなあだ名をつけてもらうことが多かった。でも勉強はきちんとしていたので、“変わり者の優等生”のような生徒だったと思う。
勉強では先生に注意されなかったので、高校の時に先生の似顔絵や先生をギャグ化した新聞とかを作ってクラスで回して、みんなでいたずらを楽しんでいた時、コツンと怒られるのが新鮮で、実はちょっと嬉しかったなんてこともあった。
高校生になると、お店の手伝いがさらに難しくなり、人口も少なくて商売にならないので、お店は畳むことになった。
正直寂しさはなく、稼げないなら仕方ないことだった。
お店を畳んだ後は、近所の漁師の家で、17時から24時くらいまで、ウニの殻剥きのバイトをし、そのあとに受験勉強。
バイトは寒くて、夜も遅い仕事だったが、自分で自立するようにやらなきゃという思いがあった。それは根底に進路のこともあったと思う。
高校卒業後の進路を決めるとき、父からは「医学部以外は学費を出さないぞ」と言われていた。どうやら根室では医学部を卒業して地元に帰って来れば学費免除という制度もあったし、稼ぎがいいからと思って勧めていたようだった。
私ももう少し頭が良かったら考えたが、今の学力と照らし合わせて進路を考えている時、
「農学部行けば、食品とか発酵とか研究できるんじゃない」
と進路指導の先生に言われ、実家が食料品を扱っていて、イカの塩辛を作るなどお店の商品を作っていたこともあり、食品が身近にあったし、特にこだわりなく消去法で岩手の農学部に進むことにした。宮澤賢治の行っていた学校というミーハーな理由もちょっとあったけれど。
大学は学費が免除の対象になって、奨学金ももらえることになったが、女子寮に入ったとはいえ生活費を稼がないとならないため、接客、家庭教師、マネキン、昼夜問わず実に様々な仕事をした。今思えばこの時かなりの人生経験をさせてもらった気がする。
勉強に加えアルバイト三昧の日々。
生活費を稼ぎすぎて、奨学金の一部が出なくなるほど、アルバイトに精を出した。
その中で、シルク印刷の会社でボールペンなどに印字する原画を制作するバイトをしていた時、少し出資して役員にならないかとの誘いを受け、大学生にも関わらず、役員として仕事をするようになった。



