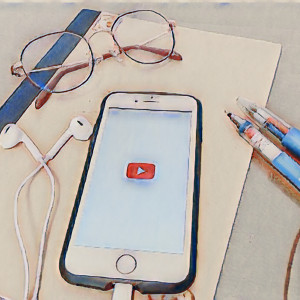ダレカの物語(大学生 クロさん)
カップ麺をサラサラと食べ終えて、またパソコンの文字面を眺める。
「この文末の言葉は気になるな、変えよう」
「この主人公の設定は後々面倒になりそうだから、この部分は消しておこう」
などとブツブツ言いながら、「ダレカの物語」は書いては消し、書いては消しを何度も繰り返して、まるでジグザグの路地裏をカーナビ無しで進むように混迷していく。私の書くスピードは多分極めて遅く、途中で混迷した道を辿れずに「完成できない」と諦めることも多い。だが、たとえそうなったとしても、ひと時経てば不思議とまた書きたいという欲求が湧いてくるのだ。
また書かれていた文字がどんどんと消えていった。
―上書き保存しました―
本を読むことは比較的好きな部類だった。活字はたくさん読んできたし、国語の試験も勉強せずに良い点数がとれていた。だから、一週間もあれば四〇〇ページほどの文庫本くらいの文量はすぐに書けそうだと甘く見ていた。特にSFは、未来に対する自由さから書きやすそうだというのと、私自身が好きだから簡単だと思っていた。暇つぶしさえできればそれでよかった。
そして、書いてみて初めて物語を書くことがこんなに大変なんだと知った。読むにはたった一分で十分な文字量が、書いてみると一日、下手をすれば一週間かかることだってある。
世界中の小説家の凄さを、身をもって知ることになった。
書いている間は、ほとんどが苦痛だ。特に完成の見込みが立たない中盤あたり。
「やっぱりこの物語なんて面白くないや。わたし才能ないんだろうな……」
なんて思うのはザラだ。
それでも、私はまた書きたくなった。なぜかわからないけど、苦痛でたまらないけど、また書きたいという欲求が私を強く抱擁してくる。
書き始めて一年以上経った今でも、これは同じことだ。
「うーん、うーん」とうめきながら、パソコン画面を見続けてどのくらい経ったのだろう。時計を見るとAM二時。眠い、寝よう。パソコンを閉じようとした時、パッと妙案が思いついた。未だ誰も考えついていないだろう、新たなアイデアだ。パソコンをまた開けてカチャカチャと文字を紡いでいく。この時は、数少ない楽しい時間なのだ。眠気なんてどっかに行ってしまえい。
―上書き保存しました―
小説を書き始めて半年ほど経ったころ、ちょうど2020年の年末あたりのことだ。世の中はジングルベルの音楽と共にコロナ第三波が叫ばれ、再度の自粛が要請されていた。SNS上にいた多くの凶器たちは、文句が多くなり不平不満を募らせているようだった。
私はようやく一つの小説を完成させた。だが、正直なところ「どうにか完成させた」に近いもので、これは果たし読み物として成立しているのか読んでみてもわからなくなっていた。この成果を誰かに見せたかった、けど見せられるほどでもないと恥ずかしい気持ちもあった。
悩んだ挙句、匿名で投稿可能なネット上のサイトに公開してみた。「つまらない」「小説としてなってない」「日本語の使い方がおかしい」みたいな批判ばかり来たらどうしようと思ったが、それでも良い経験だと自分を言い聞かせた。